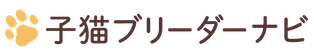健康維持の最も分かりやすい方法の1つが、適正体重・体型の維持です。
愛猫には常に健康でいてもらいたいもの。
本記事では、成長に伴う子猫の体重推移と猫種ごとの適正体重を紹介するとともに、適正体重・体型を維持するための方法を解説します。
猫の平均体重表について
| 週齢・月齢 | 体重 |
|---|---|
| 生後0週 | 約100g |
| 生後1週間 | 約150~200g |
| 生後2週間 | 約200~300g |
| 生後3週間 | 約300~400g |
| 生後1ヶ月 | 約400~500g |
| 生後2ヶ月 | 約950g~1kg |
| 生後3ヶ月 | 約1.0~1.5kg |
| 生後6ヶ月 | 約2.5~3kg |
| 生後9ヶ月 | 約3~3.5kg |
| 生後12ヶ月 | 約3~5kg |
猫は生まれてから1歳頃まで成長を続けます。
特に、生後間もない子猫は日に日に体重が増え、性別や猫種による違い、個体差はありますが、生後2週間で体重はおよそ3倍まで増加します。
種類別の猫の適正体重
| 品種名 | オスの体重 | メスの体重 |
|---|---|---|
| アビシニアン | 3~5kg | 3~5kg |
| アメリカンカール | 2.5~4.5kg | 2.5~3.5kg |
| アメリカンショートヘア | 3~6kg | 3~5kg |
| エキゾチックショートヘアー | 3~5.5kg | 3~4kg |
| エジプシャンマウ | 3~5kg | 3~4kg |
| オシキャット | 3.5~6.5kg | 3~5.5kg |
| オリエンタルショートヘア | 3~4kg | 3~4kg |
| サイベリアンフォレスト | 4~8kg | 4~6kg |
| ジャパニーズボブテイル | 3~4.5kg | 3~4.5kg |
| シャム(サイアミーズ) | 3~4kg | 3~4kg |
| シャルトリュー | 4~6.5kg | 3~5kg |
| シンガプーラ | 2~3.5kg | 2~3.5kg |
| スコティッシュフォールド | 3~6kg | 3~5kg |
| セルカークレックス | 3~6.5kg | 3~5kg |
| ソマリ | 3~5kg | 3~4.5kg |
| トンキニーズ | 3~5kg | 3~4.5kg |
| ノルウェージャンフォレストキャット | 3.5~6.5kg | 3.5~5.5kg |
| バーマン | 3~6.5kg | 3~5kg |
| ヒマラヤン | 3~5.5kg | 3~5kg |
| ブリティッシュショートヘア | 3~5.5kg | 3~5kg |
| ペルシャ | 3~5.5kg | 3~5kg |
| ベンガル | 3~6kg | 3~5kg |
| マンチカン | 3~6kg | 3~6kg |
| メインクーン | 3.5~6.5kg | 3~6kg |
| ラガマフィン | 4~7kg | 4~6kg |
| ラグドール | 4~7kg | 4~6kg |
| ロシアンブルー | 3~5kg | 3~5kg |
猫の体重は、品種によって異なります。
上記表では、代表的な猫種を50音順に掲載し、それぞれオスとメスの体重を比較してみました。猫種別に見ていくと、同じ品種でも適正体重に幅があることがわかるでしょう。
そのため、小型猫と言われている品種でも、大きい個体は中型猫と同等の体重であることも珍しくありません。
痩せすぎ?肥満?体型チェック

上述したように、同じ猫種であっても適正体重に幅があるため、一概に「この体重だから大丈夫」とは言い切れません。
では、愛猫の体重や体型が適正かどうか、どうやって判断すれば良いのでしょうか。
体重の量り方
猫はおとなしく体重計に乗ってくれません。そのため、猫の体重を量るときは、飼い主が猫を抱えて体重計に乗り、そこから飼い主さん体重を引いてください。そこから導き出された数値が、猫の体重になります。
また、猫をクレートやベッドに乗せて、それごと体重計で猫の重さを量る方法も良いでしょう。この場合、そこからクレートやベッドの重さを引けば猫の体重が分かります。
体型チェック方法
猫の肥満度は、単純な重さだけでは分かりません。
そのため、見た目の体型や触った時の肉付きも合わせて、肥満度を判断する必要があります。
- 肋骨が感触がはっきりわかる=標準
- 肋骨の感触がかろうじてわかる=やや肥満
- 肋骨の感触がない=肥満
- くびれがある=標準
- くびれが分からない=やや肥満
- ウエストが膨らんでいる=肥満
- お腹のラインが床とほぼ平行=標準
- 下腹部がぽっこりしている=やや肥満
- お腹が膨らみ弛んでいる=肥満
痩せすぎの場合の対処法
猫が痩せすぎの場合、考えられる原因は食欲不振や何らかの病気、フードが合わないなどが考えられます。
愛猫が痩せすぎで心配になったら、まずはなぜ痩せたのかその原因を知ることが先決です。
日常的に猫の様子を観察して、気になることがあればメモを取ると良いでしょう。
仮に動物病院を受診する必要に迫られたとしても、愛猫の様子を細かく説明することができるので、問題解決の近道になります。
では、原因ごとの対処法を確認していきましょう。
そのため、それまでと同じ食生活ではどうしても痩せていってしまうので、フードを老猫用の消化吸収が良い物や高カロリーの物に切り替えると良いでしょう。これにより、1食で摂取できるカロリーを増やすことができます。
また、高齢になると一度に食べられる量が減ることもあるので、1日の食事回数を細かく分けるのも有効です。
普段と様子が違ったり「最近痩せてきたかも…」と思ったりしたら、一度動物病院で診察してもらいましょう。
その場合は、フードをふやかしたり咀嚼しやすいウェットフードに切り替えたりすると良いでしょう。
肥満の場合の対処法
一般的に、体重の維持に必要なエネルギーの70%程度にすれば理想的な減量になるといわれています。肥満対策のために開発された療法食を利用するのも有効なので、獣医師に相談してみるのも良いでしょう。
猫は上下運動を好むので、キャットタワーを置くなど飛んだり跳ねたりできる環境を作ってあげられれば理想です。
ただし肥満の猫に激しい運動をさせると、関節や心臓に大きな負担がかかるので、無理のない範囲で行ってください。
体重の推移を確認することができるだけでなく、体重を意識することにもつながります。
まとめ

多くの動物にとってそうであるように、猫にとっても肥満は万病の元。かといって痩せすぎも健康には良くないため、適正な体重を維持することが大切です。
今回は、成長に伴う子猫の体重推移と猫種ごとの適正体重、体型維持の方法を解説してきました。
愛猫の健康を守ってあげられるのは、飼い主であるあなただけです。
いくらかわいいからといってただ甘やかすだけではなく、厳しさを持って接することが、愛猫を守ってあげることに繋がります。
今回の内容を参考に、適正な体重と体型を維持させられるように努めてください。