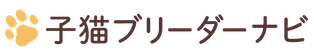猫を飼うとさまざまなお手入れが必要になりますが、耳掃除もそんな大切なお手入れの中の1つです。
耳は特にデリケートな部分なので、触られることすら嫌がる子も多く、お手入れの仕方が下手だとケガをさせてしまう恐れもあります。
本記事では、そんな猫の耳掃除について解説します。
耳掃除は必要なのか?

猫の耳には自浄作用があるため、基本的には放っておいても問題ありません。余程汚れが気になるときは、その部分を拭いてあげるだけで基本的には十分でしょう。
耳の形によって必要性が異なる
猫の耳は多くが立ち耳ですが、中にはスコティッシュフォールドのような「折れ耳」の猫種も存在します。
立ち耳は通気が良く蒸れにくいのでそれほど汚れることはありません。しかし、折れ耳は通気性が悪いため蒸れやすく、耳の中で雑菌が繁殖しやすくなります。
そのため、立ち耳の猫種よりも折れ耳の猫種の方が、耳掃除は重要といえるでしょう。
定期的に耳の状態をチェックして、汚れすぎないよう掃除をしてあげてください。
黒い汚れがあるときは注意
猫の耳に茶色い汚れが少量付いている程度であれば、正常な状態です。
しかし、黒い耳垢が大量に付いている場合、何かの病気の可能性が高いので、「汚れているだけ」と放置するのは良くありません。
耳ダニに寄生されていたり、マラセチアや真菌に感染していたりする恐れがあります。
耳をチェックする場合は、汚れの色や量まで確認するようにしてください。
耳掃除のやり方は?

人間の耳と猫の耳では構造が違うため、初心者はどうやって掃除してあげれば良いのか分からないでしょう。場合によっては、やり方が悪いせいでケガをさせてしまう危険もあります。
ここでは、デリケートな耳を上手に掃除するための方法を解説します。
準備するもの
- ガーゼ/コットン
- 綿棒
- 洗浄液(イヤークリーナー)
ガーゼで拭き取る方法
濡らしたガーゼや綿棒で、丁寧に汚れを拭き取ってあげましょう。
基本的には見えている部分を拭き取るだけで問題ありません。奥の方まできれいにしようとすると、汚れを耳の奥に押し込んでしまったり、痛い思いをさせたりする恐れがあるので注意してください。
汚れ方がひどくお手入れの時間が長引くようなら、ある程度で止めて翌日に持ち越しましょう。
洗浄液(イヤークリーナー)を使用する場合
猫の耳掃除に、洗浄液やイヤークリーナーを使う飼い主さんも多いでしょう。
これは、耳の穴に直接液を垂らしたり液を含ませたコットンで耳の奥を拭ったりすることで、耳の奥まできれいにすることができる耳掃除グッズです。
愛猫が耳掃除に慣れてきたら、奥まできれいにするために使用すると良いでしょう。
使い方は、直接耳の穴に液を数滴垂らし、少し待ってから耳の付け根あたりを軽く揉みます。これで耳道の汚れが浮き上がってくるので、コットンで拭き取れば完了です。
この際、強く揉むと鼓膜を傷つけてしまう恐れがあるので、力加減には注意しましょう。
嫌がるときはどうすればいい?
耳掃除を嫌がる猫は多いもの。しかし、頻度を減らすことはできても、一切耳掃除をしないというわけにはいきません。
もしも愛猫が耳掃除を嫌がるようなら、その場は引くことも大事です。耳掃除を嫌がられないように、猫がリラックスしている時を見計らって、ごく短時間でできる限りのお手入れをしてあげましょう。
嫌がっているのに、無理に最後までやり終えようとすると、ケガをさせてしまう恐れがあります。
また、一度でも嫌な経験をしてしまうと、それ以降耳掃除の準備や素振りを見るだけで逃げてしまうので、嫌がる場合は日を改めて挑戦すると良いでしょう。
耳掃除の頻度

耳掃除は全くしないのも良くありませんが、やりすぎると炎症を起こして外耳炎などになってしまう恐れがあるので、耳掃除の頻度には注意しましょう。
1週間に1回は耳の状態を確認し、汚れ具合によって耳掃除をするかどうか判断してください。多くても1~2週間に1回、あまり汚れが気にならないようであれば、月に1回程度でも問題ありません。
立ち耳か折れ耳か、汚れやすさにも個体差があるので、愛猫の状態によって耳掃除の頻度を調整してあげられればベストです。
まとめ
猫と暮らしていれば、さまざまなお手入れをする機会があるでしょう。
耳掃除はそんなお手入れのうちの1つですが、ブラッシングなどと比べても難しいお手入れといえるでしょう。
今回の内容を参考に、愛猫に負担をかけないよう上手に耳掃除をしてあげてください。